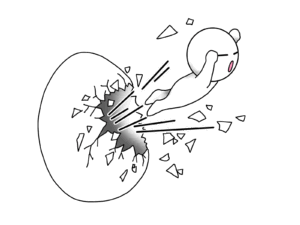教育に価値観のアップデートを
Englishbuds 管理人 MommyKayoです。
先日、とても嬉しい出来事がありました。
読み書きに困難が見られるお子さんを1年半ほど指導してきたのですが、この1ヶ月で明らかな変化が見えてきたのです✨
ここ最近ぐんと読みやすく、書きやすくなってきている様子が見られるのです!
もちろん、まだ時々読み間違えることはあります。(人間だもの)
けれど以前のような「たどたどしさ」はずいぶん減り、文章を自然なテンポで読めるようになってきました。さらに、magic eを含む単語をディクテーションで書き取れるようにもなっています✨
努力の積み重ねはもちろんですが、学びには“閾値”を越える瞬間があると感じます。ある日ふっと理解がつながり、一気に世界が開けるような瞬間。その場に立ち会えることが、私には無上の喜びです💛
息子の時にも同じような体験をしましたし、これまでJollyの指導をさせてもらう中でも、何度もその“閾値越え”を見てきました。私の中ではもう「閾値理論」は確信になっています(笑)。
子どもによって理解のスピードも、つまずき方も、必要なサポートも本当に違います。だから「一律にこの方法で」と決めつけるのは無理があります。
とはいえ「一律の対極は完全個別対応だ」という考え方も現実的ではありません。すべてを個別化してしまったら、集団教育そのものが立ち行かなくなってしまいますからね…
では「画一的」とは何が問題なのでしょうか。
私が感じるのは、一つの感覚器に頼りすぎた教育法が限界に来ているのではないか、ということです。
「この方法でやれば万人に有効だ」というようなものはないと思うのですよね。
Jollyが多くの子どもに効果を発揮しているのは「多感覚」を取り入れているからだと思います。音を聞くだけではなく、絵を見て、手を動かし、ストーリーと結びつけて学ぶ。多岐にわたるプロセスのおかげで、どの子の得意不得意にも対応でき、可能性を狭めない。多感覚的でフレキシブルな方法を取り入れることで、取りこぼしのない学びが可能になるのだと実感しています。
ここでいつも考えさせられるのが、「読み書き困難」や「学習障害」をどう捉えるかということです。もちろん程度の差はあるので一概には言えませんが、「特別支援」と大きく区切らなければならないのか…という疑問があります。
私が言いたいのは、子どもの“凸凹”の「ボコ」の部分にすぎないのでは、ということ。そんなに特別なものではなく、誰にでも得意不得意があるという延長線上で考えられるはずです。
アプローチを変えてあげれば埋まる部分もあるのに、「特別」としてしまうことで“特別感”が強まり、周りも本人も「自分のことではない」と意識的に無意識的に対象外にしてしまって、必要な支援が届かないのではないか。そんな危うさを感じています。
実際、私は特別支援の専門家ではありません。元教員ではありますが、特別支援の経験はゼロに近く、体系的に勉強したこともほとんどありません。
それでも、多感覚なアプローチを工夫し、子どもの成長を信じて見守っていくと、子ども自身の力が表れてくる場面を何度も見てきました。私が特別なスキルを持っているわけではなく、単に観察しながら一番響きそうな方法を厚めに取り入れているだけ。つまり誰でもできることだと思うのです。
読み書き困難で困っている子は、表面化していないだけで実際にはかなりの数いると思います。「努力が足りない」「頭が悪い」と切り捨てられてしまっているケースも少なくないのではないでしょうか。ほんの少し教育の価値観をアップデートするだけで、必要な支援が届くのになぁと感じます。
やっぱり本来は公教育でこうした部分をフォローしてもらえるのが理想です。しかし現状の教育システムはまだまだ画一的。日本の教育は、かつて「均質な労働者を育てる仕組み」としては機能していたのかもしれませんが、今はそのやり方が限界に来ていますし、そもそもこれからの時代には合わなくなっていると感じます。
「普通学級」と「特別支援」という区分も、その象徴のように思います。本来なら役立つはずの方法も、“特別”というラベルがついた途端に届きにくくなってしまいます。道村式の指導法や特別支援用の漢字教材なども、多くの子に有効なのに「特別」という括りで遠ざけられてしまう現状があります。
特別って一体なんでしょう。。。
ほんの少しの工夫や別のアプローチで子どもを助けられるなら、それは「特別」ではなく「誰にでも自然に届く学び」であるべきだと強く思います。
教育のユニバーサル化進みますように、と願うばかり…
私自身、今はPhonicsとGrammarのカリキュラムをアップデートしている最中です。大切にしているのは多感覚さ。どの子の可能性も潰さないこと。そして「なるほど!」という気づきを毎回提供できること。得意はもっと伸ばし、苦手は特性に合った方法で支えられるように。
「このやり方が絶対なのだ」というような思い込みを排除し、子どもたちが自分のペースで育っていけるような工夫を重ねていきたいと思っています。
世の中の価値観は日々アップデートされています。働き方や生き方に多様性が求められる今、教育もまた変わっていかなければなりません。「特別」か「普通」かという線引きに縛られず、もっとフレキシブルで多感覚的なアプローチを誰にでも自然に届けられる教育が広がればいいなと願っています✨
Englishbudsでできることは小さなことかもしれませんが、まずは私の中でアップデートされた価値観を反映して、子どもたちを支援していくことを愚直に続けていきたいと思います。
おうち英語こそ、子どもの個性に合わせてカスタマイズできる極みですからね!
今日の教材更新、ガンバリマスー💛
にほんブログ村