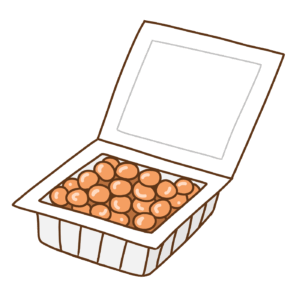🥢「音読すれば安心」?──“納豆理論”で考えるおうち英語の落とし穴
Englishbuds 管理人 MommyKayoです。
教育業界では、「音読はいい」「毎日続けましょう」というメッセージを本当によく見かけます。
たしかにそれは真実で、音読には“声に出すからこそ”得られるメリットがたくさんあります。
でも、日本人って「いい」と聞くと、つい全振りしがちなところがありませんか?
みのもんた世代ならわかると思うのですが、「納豆が体にいい」とテレビで言われた瞬間、スーパーの納豆が棚から消えるあの現象です。(年齢トラップw)
音読についても、ちょっとそれに似た空気を感じることがあります。
■ 音読が「いい」と言われるのには、ちゃんと理由がある
まず、音読の良さをきちんと認めておきます。
子どもが声に出して読むとき、実は同時にいろいろなことをしています。
・目で文字を追う(視覚)
・自分の声を聞く(聴覚)
・口や舌、息をコントロールする(運動感覚)
心理学では、自分で答えをつくったり、再現したりするほうが記憶に残りやすいことを「生成効果(Generation Effect)」と呼ぶそうです。
また、声に出して読むことで覚えやすくなる現象は「音読効果(Production Effect)」として報告されています。
つまり音読は、
・フレーズや表現が頭に残りやすくなる
・「自力で読めた!」という感覚が得られて自信になる
・発音やリズムを、自分の耳で確認できる
といった意味で、とても優秀な練習方法です。
ここはしっかり「音読、すごく良い」と言っておきたいところです。
■ でも「音読させていれば安心」という思い込み
一方で、おうち英語を長く見てきて感じるのは、音読が
「子どものための練習」
であると同時に
「親の安心材料」
にもなっている、ということです。
・どこまで読めているのか
・どのくらい理解しているのか
・今日ちゃんとやったのか
声に出して読んでくれれば、
見える・聞こえる・管理しやすい。
親としてはすごく安心できるやり方ですよね。
それ自体を私は否定しません。
ただ、その安心感があまりに心地よすぎると、気づいたときには
「音読こそが多読」
「音読していない時間は“読んでいない”時間」
のような感覚になってしまうことがあります。
ここで、さっきの納豆理論です。
納豆が体にいいからといって、
朝も昼も夜も納豆だけ食べ続けたら、さすがに栄養は偏ります。
音読も同じで、「いいから」といってそこだけに頼りすぎると、
他の大事な“読みの力”を育てる余白がなくなってしまいます。
■ やりすぎ音読で起こりがちなこと
音読は、脳にとってけっこう負荷の高い作業です。
文字を目で追いながら、声を出しながら、意味も処理しているので、頭の中はフル回転状態です。
教育や心理の分野では、こうした「頭の中の処理のしんどさ」を
認知負荷(Cognitive Load)と呼ぶそうです。
・難しすぎる本を、最後まで音読させ続ける
・意味があやふやなまま、とりあえず声に出させる
こういう状態が続くと、子どもの頭の中は「処理するだけで精一杯」になってしまい、
内容があまり残らなかったり、「読む=疲れる」という印象だけ残ったりします。
おうち英語ならではの副作用としては、
・「誰かに聞いてもらうための読み」ばかりになりがち
・静かに自分のペースで読み進める経験がなかなか積めない
・チャプターブックに上がりたいのに、いつまでも音読で足踏みしてしまう
といったことが起こりやすくなります。
■ 音読は「多読メニューの一品」くらいでちょうどいい
じゃあ音読はやめたほうがいいのか?というと、もちろんそうではありません。
私が言いたいのは、
音読はやっぱり良い。
でも「主食全部音読」はやめておこう。
というバランスです。
音読は、
・多読の中にある「読み方のひとつ」
・親が理解度を確認するための「方法のひとつ」
・子どもが自信を持てるきっかけになる「手段のひとつ」
といった位置づけで考えておくのが、おうち英語的にはちょうどいいと感じています。
そうしておくと、
・静かに黙読する時間
・大人に読んでもらう時間(読み聞かせやオーディオブック)
・ただ絵を眺めて物語の世界に浸る時間
といった、他のインプットの時間もちゃんと守ってあげられます。
■ 黙読は「サボり」ではなく、ステップアップのサイン
ここでもうひとつ、声を大にして言いたいのが、黙読の意味です。
子どもが黙って本を読んでいると、
「本当に読んでるのかな?」
「サボってないかな?」
そんな不安が、どうしても頭をよぎりますよね。
でも、冷静に考えると、黙読って
「声に出さなくても読めるようになった」
という成長のサインなんです。
声に出していたときよりも速く、頭の中で処理できるようになったからこそ、
黙読に移行していきます。
これは、読みのスピードや理解の速度が上がっている証拠でもあります。
なので、ある程度スラスラ読めるようになってきたら、
・音読:短いフレーズ、新しい表現の定着用に少しだけ
・黙読:物語を楽しみながら先へ進む「メインの読み方」として
というように、役割分担をさせていくのがおすすめです。
■ 納豆も音読も、「ほどほど」が一番おいしい
音読には、生成効果や音読効果といった形で、心理学的にも裏づけがある学習法です。
親にとっても、子どもにとっても、うまく使えば頼もしい味方になってくれます。
でも、「いいらしい」と聞いた瞬間に、全部そこに寄せてしまうのは納豆と同じ。
おうち英語メニューの中の「一品」くらいに考えておくほうが、
結果的に読みのバランスが良くなります。
音読も、黙読も、聞く時間も、ぼーっと眺める時間も。
いろんなインプットのかたちを、その子のペースに合わせて組み合わせていけますように。
納豆も音読も、「ほどほど」が一番おいしい。
それくらいの感覚で、おうち英語に取り入れていけたらいいなと私は思っています。
にほんブログ村