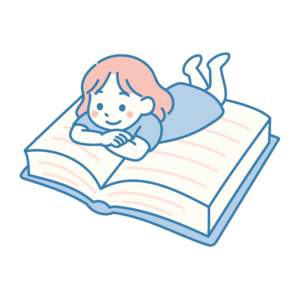おうち英語視点で「読みの自動化」を考える
フォニックスを駆使して読んでる子を私は見たことない
としばしばこれまでも書いてきました。
もちろん、最初の“手がかり”としてPhonicsは有効です。
でも「b+a+t=bat」みたいなブレンディングをしていたらスラスラ読むことなどできません。
最近つくづく思うのは、
結局、読みを支えているのは
Sight Word 化=読みの自動化
ということです。
🧠 Sight Wordって、実はすごい処理
Sight Wordと聞くと、「頻出語でしょ?」とか「見て覚えるやつでしょ?」と思いがち。
しかし、これはただの丸暗記ではないようです。
Sight Wordはアメリカの教育心理学者 Edward Dolch が1940年代に提唱した概念で、
「文章中によく出る基本語で、子どもが音読時に瞬時に認識できる語彙」
という定義があります。
現在では、視覚・音韻・意味の3つが
脳内で瞬時に統合されて自動で処理される単語と捉えられています。
これは脳科学的にも、視覚野 → 側頭葉(音韻処理)→ 意味連合野 という
複雑な処理回路が繰り返し使われた結果、ショートカットのように処理される状態のことだそうです。
むむむ。学問的には難しいですねw
📚 じゃあどうすればSight Word化するの?
学問的なことはいいと。
じゃあ、具体的にはおうち英語でどうしたらいいんだ?!ですよね。
私もおうち英語初期、Sight Wordのことをよくわかってなくて
“Sight Word絵本”なるものを買ったことがあります。
でも…正直、つまらず死蔵化(笑)
「The cat is big.」「I see a dog.」みたいな短文がただ続いて、
ストーリー性もなくて、全然盛り上がらない。
当時の私は、
「なんやねん“Sight Word”…?」と苦い顔で本を閉じた記憶があります。
Sight wordの絵本はたくさんAmazonでも販売されているので
私と同じように「とりあえず買ってみた」という方も多いのではないかと。。。
Sight Word Bookがたくさん出版されているように、
意図的に読みを練習させる“学習型”のSight Word化もあると思います。
でも、おうち英語では
「もっと自然なインプットを基本軸にすべきなのでは?」
と思います。
やっぱり絵本多読+意味あるやりとりで
時間をかけて「Sight Word化」していくのが王道だと思っています。
👀 でも、気をつけたいのは“学習タイプ”
ただし、ここでひとつ注意点。
Sight Word化って、すべての子が自然にできるわけじゃないとも思っています。
中でも、聴覚優位な子の場合、
「聞けば理解できるけど、文字に意識が向かない」
という特徴があり、視覚と結びつける自動化処理が進みにくい傾向があります。
そういう子には、
👆 意図的に「文字を見る時間」を作ってあげることも大切かと思っています。
・読んでるときに単語をなぞってあげる
・絵本に出てきた単語を繰り返し音読する
・語りかけの中で「これ、〇〇って書いてあるね」と指差す
こうした“軽やかな読みサポート”は、
強制感を出さずにSight Word化を後押しする工夫になります。
✨ 最後に:読みの流暢性は、“処理の省エネ化”の結果
読みは、努力だけではなく、脳の“自動処理”で支えられている面が大きいようです。
音・文字・意味の3つが脳内で何度もつながって、
やがてショートカットのように処理されるようになる。
それが、Sight Word化。
おうち英語では「量で勝負」が合言葉のようになってますが、
その“量”がちゃんと意味づけされていれば、
この自動処理=読みの流暢性は確実に育っていきます。
だから、焦らず、Phonicsの効果も信じつつ、でもSight Word化のプロセスも大切にして
わが子の「読みの力」、じっくり見守っていきましょう😊
にほんブログ村